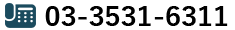Q8:『相続税対策』を講じた事例を教えてください。2019.09.06
A8:『相続対策』と『相続税対策』とがあることについては、Q5でお答えしたとおりですが、
『相続税対策』の事例として、賃貸住宅を併設した自宅の建設をご紹介します。
既に父親が他界されて、母親だけが土地を所有していました。
その土地に母親の自宅を建設しました。
まず、母親の財産の全体を評価すると、約1億5,000万円でした。
子どもが二人でしたので相続税が1,200万円でしたが、
相続税が改正された場合には、1,840万円と高額になるため、相続税対策を講じることになりました。
自宅が老朽化していたため、自宅の建て替えを母親の自己資金と借入金で建設することにしました。
また、借入金の返済に充てるため、建物の一部を賃貸住宅としました。
母親が預貯金を取り崩して自己資金を支出することと、残りの建設資金を借入れたこと、
賃貸住宅部分の土地の評価が貸家建付地として減額できたことで、母親の財産の全体を、
新しい建物の価値を考慮しても約1億1,000万円まで減額することができました。
これによって相続税は、改正後の場合で1,840万円から960万円へと、880万円が減額される予定です。
(現行の相続税では1,200万円から500万円に減額。)
被相続人となる予定の親が、借入金をして賃貸住宅を建設する手法は『相続税対策』の基本的な手法ですが、
とても大切なことがひとつあります。
それは賃貸住宅が長期に安定した事業として賃貸運営できる事業計画であることです。
『相続税対策』ばかりに気をとられて多額の借入金をし、相続税は支払わずにすんだものの、
子どもが借金返済に苦労するケースも多くありますので、賃貸住宅の事業計画には充分な検討が必要です。
最新記事
- 12月13日 秋の金沢旅行
- 11月14日 防災功労者として表彰されました
- 10月21日 10/25(土)開催「第22回子どもとためす環境まつり」
- 10月11日 生まれ変わった旧晴海鉄道橋
- 09月26日 江戸城の田安門、半蔵門、虎ノ門
カテゴリー
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年1月
- 2017年10月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年1月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2014年9月
- 2013年8月
- 2012年8月