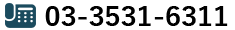Q2:『相続』によって親族が争うと聞きました。どのような背景からですか?2019.09.06
A2:『相続』に関する重要な法律は、昭和22年(1947年)の
民法大改正(親族編・相続編の全部改正)によって確立されました。
それ以前の旧民法は「家族制度」であり、家は戸主と家族とにより構成され、
戸主は戸主権という一家統率の権力を有し、家族に対して身分上の統制力を持つものでした。
『相続』についても「家督相続」により、戸主権の承継として長男一人が遺産の全部を相続し、
その家を守るという制度でした。
新しい民法は、「親族共同生活を現実に即して規律すること」を目的として策定されました。
同時に『相続』についても「均分相続」が用いられ、
兄弟姉妹が平等に遺産を相続する権利を有することになりました。
しかし、その後半世紀近くの相続事例の多くは、古くから日本人に定着した「家督相続」の考え方に基づき、
「長男が相続するのがあたりまえ」と判断され、同時に対処されてきました。
また、「相続の事は外には漏らさない」との考えから表面化することは少なく、
たとえ表面化しても、「相続は金持ちにしか関係ない」などの誤った解釈から、
『相続』というものが社会に目立って取り上げられることはありませんでした。
しかしながら、昭和22年の民法改正前後に生まれた方々が古希に近づく現代においては、
「均分相続」の考え方も定着しており、
また、核家族化の進行に伴い、遺産分割を巡って『相続』トラブルが増加する傾向がでてきました。
様々なメディアも『相続』を「争続」などとして取り上げ、
相続問題が身近に捉えられるようになりました。
最新記事
- 12月22日 環境にも家計にも優しい「EPS断熱材」の魅力
- 12月13日 秋の金沢旅行
- 11月14日 防災功労者として表彰されました
- 10月21日 10/25(土)開催「第22回子どもとためす環境まつり」
- 10月11日 生まれ変わった旧晴海鉄道橋
カテゴリー
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年1月
- 2017年10月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年1月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2014年9月
- 2013年8月
- 2012年8月