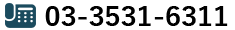Q3:『相続』の手続きにはどのようなものがありますか? 2019.09.06
A3:一般的には、以下の手続きがあります。
① 亡くなったことを区役所に届けることから始まります。
② 被相続人の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得して相続人を特定します。
③ 並行して、被相続人の財産や権利や義務などを整理します。
④ その財産や権利や義務などを決められた方法で評価し、その合計が一定の基準を超える場合には、
相続税を納税する必要がありますので、相続税の申告の準備と、その納税の資金の用意を考えます。
⑤ 借金などが多く、資産や権利など合計が負(マイナス)になるようであれば、相続の放棄などを検討します。
相続放棄は、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
⑥ 所得税の準確定申告をします。
1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、
亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、申告と納税をします。
⑦ 財産や権利などを相続人で分け合うことについて、遺言書があればその内容に基づき、
そうでない場合は、相続人で話し合って決め遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の捺印と、印鑑証明書の添付が必要です。
⑧ 相続税がある場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告し納税をします。
(1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が申告期限です。)
⑨ 納税資金を捻出するために不動産を売却する場合には、不動産の名義変更(相続登記)や、
土地の境界の確定、買主側の融資などの手続きに必要な時間を考慮して、
売買契約を締結し引渡をする必要があります。
⑩ 財産や権利などの名義変更は、遺言書や遺産分割協議書に基づき、それぞれ手続きをします。
不動産の名義変更は所轄の法務局で、銀行口座はその口座の金融機関で、
権利などは、契約であれば契約書の名義変更について契約の相手と合意し、書面を残します。
最新記事
- 12月22日 環境にも家計にも優しい「EPS断熱材」の魅力
- 12月13日 秋の金沢旅行
- 11月14日 防災功労者として表彰されました
- 10月21日 10/25(土)開催「第22回子どもとためす環境まつり」
- 10月11日 生まれ変わった旧晴海鉄道橋
カテゴリー
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年1月
- 2017年10月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年1月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2014年9月
- 2013年8月
- 2012年8月